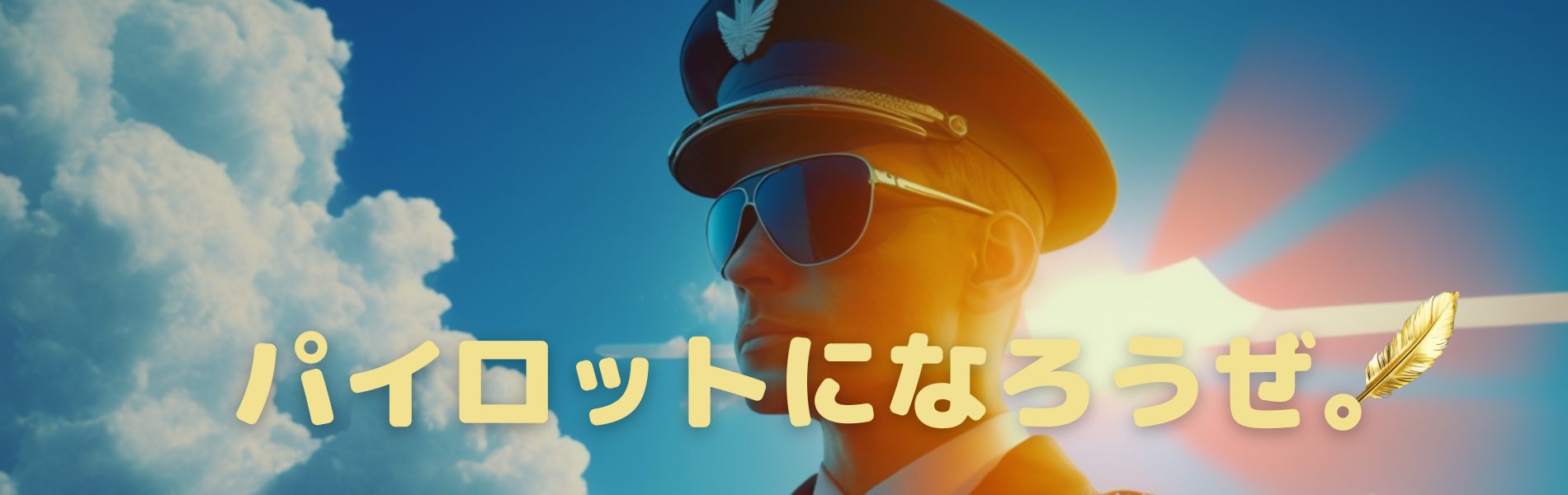もし油圧がオールロスしたらどうしますか?
初めまして^ ^私は都内に住む女性です。
この前元パイロットさんと飲む機会があり、飛行機のことについて色々ききました。
もし油圧がオールロスしたらどうしますか?
『油圧はオールロスなんかしない。俺は整備士に絶大なる信頼性をしている。』
とおっしゃっていました。実際に123便での事故などもあったので、この方なりの緊急時のことを聞きたかったですが主さんならどうされますか?
こんなことを聞いてしまい申しわけありません。ただどうしても聞きたい質問なのです。
お仕事頑張ってフライトファイトです。
By ななさん
回答
ななさん、ご質問ありがとうございます。
息子をパイロットにしたい眼科医さん、ありがとうございます。
先を越されてしまいましたが、こちらの記事にコメントを転載しておきます。
ハイドロオールロスは123便に近い状況ですね。
事故の後、JALの担当者がBoeingに訪問したところ、何十回も練習したであろうテストパイロットが123便と同じ状況でシミュレーターでパワーだけを使ってなんとか生還したのを見せて、『どうだ?うちは悪くない』みたいなことを見せたらしいです。
Boeingはパイロットの中では後世に語り継がれるような恥を晒したわけですが、後世のパイロットには教訓になりました。
『ハイドロオールロスの場合にはパワーを使って帰ってくることも不可能ではない。』
ただこれはパイロットが担当する機材によって答える内容が違うと思います。
B737やB767は操縦桿とケーブルで舵面が繋がっていて、ハイドロが全てなくなってもコントロールが効きます。めちゃくちゃ重たいですけどね。
どれくらい重たいかというと、着陸の時にはパイロット二人で操縦桿を引かないとフレアーできないレベルです。
僕もシミュレーターでやったことがあって、エレガントな着陸はできないですが、生還できる可能性は高いと思います。
他の飛行機では、上の例のようにパワーを使って操縦することになるでしょう。
右翼のパワーを強くすると右の翼が引っ張られて、飛行機は左旋回します。
逆も然りです。
細かい操作は困難を極めると思いますが、山から遠ざかることは難しくないと思います。
また、これも飛行機によりますが、電源が生きていればトリムが使えます。
トリムは舵面の端っこについている小さな舵面で、本来は操縦にかかる力を弱めるために使いますが、これも操縦に使えます。
眼科医さんがコメントで触れられていますが、運航の現場では『想定外の事態』『今まで誰も経験したことがない事態』が起こり得ます。
そういう意味では、ハイドロオールロスは一度起こったことなのだから、今後のパイロットは対応できなければなりません。
しかし本当の想定外の事態に対応するのはほんとに難しいことなのですが、世界中で行われている最近の訓練はこれに注目されていて、MCCやCBTAと言われるものがありますが、『既存の規定やトラブルシューティングでは対応できない事態に対応する能力』を養うことが課題とされています。
具体的な話はこの辺の話になります。パイロットに必要な能力
しかし大切なのは、全てのパイロットがちゃんと過去の事故を研究して、『自分だったらどうやって生還するか』『類似事例にいかに対応できるのか』
それを考え続けるしかないのだと思います。
以上。最近質問が少なくて話題に困っているので、またなんでも質問してください。