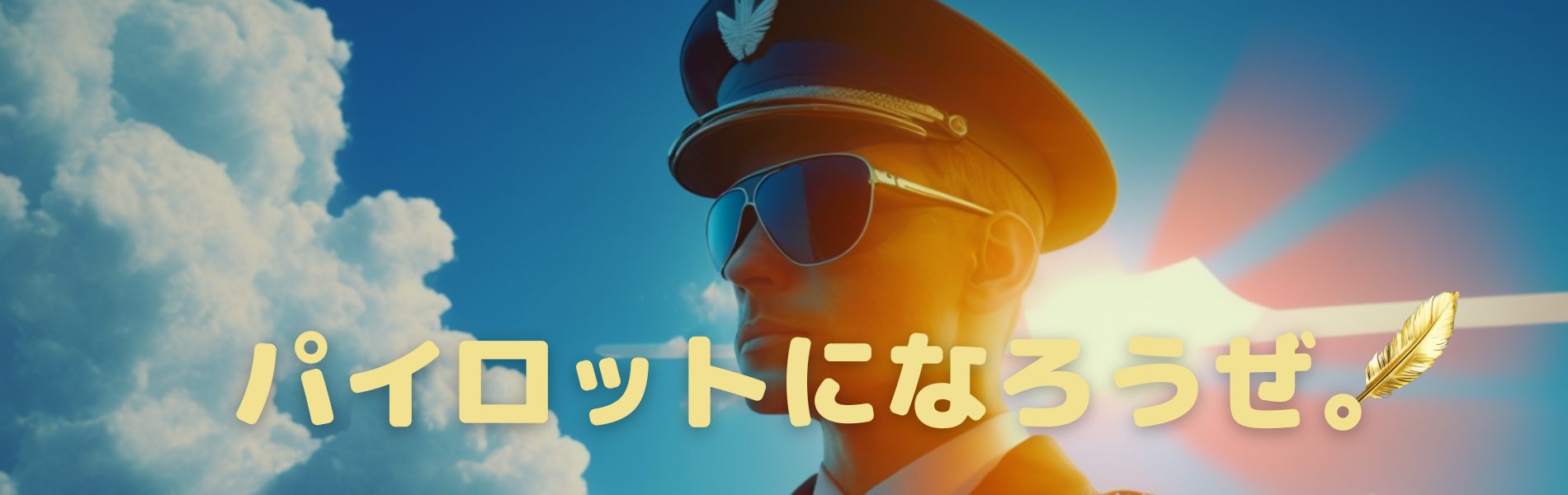将来的なパイロット職の雇用、人工知能との関わりについて意見を下さい。
こんにちは。
つい最近、パイロットという職業に興味を持ち始めた大学3年生です。
長文を書いてしまったこと深くお詫びします。
お伺いしたいことは近い将来に急激に進化するであろう人工知能についてです。
極一部の学者が2045年に人工知能が人間の脳を超える知能を持つことを予測しています。
私はこれを鵜呑みにしているわけではありませんが、将来的には人工知能が既存の職を人間から奪うことはあるかと考えています。
すでに飛行中ではオートパイロットシステムなどが導入されているとは聞きますが、これに加えて離着陸や飛行ルートなども人工知能が単独でこなせるようになると人間パイロットが必要とされなくなる可能性はあるのではないでしょうか。(人間が人工知能の補助或いは計器のチェックをすることはあるかと思いますが)
ここで下記のサイトを読み疑問が生まれるのですが、
http://wired.jp/2004/03/01/コンピューター制御でパイロット不要の旅客機は/
これらのサイトの「航空業界では、パイロットが操縦せずに旅客機を運航することが実現可能かどうか、激しい議論が繰り広げられている。」の議論は具体的にどのような内容であるのか。
「満員の旅客を乗せた無人操縦機など想像できないという」エアバス社の見解はどういった根拠に基づくものであるのか。
管理人さんが知る限りで結構ですので、管理人さんの見解をお教え下されば幸いです。
また、私は現代技術で代替可能であるように見える鉄道の運転手職にこの疑問の答えがあるように思っています。
By 大学3年生さん
回答
大学3年生さん、ご質問ありがとうございます。
非常に面白いテーマですね、しかも議論の方向性や根拠が明確に示されていて秀逸な質問です。
まずは僕の考えから述べると、遠い未来にパイロットがいなくなることがあるかもしれないけれど、少なくとも僕が生きてる間はないだろうなーと思っています。そう考える理由はたくさんあって何から話そうか迷いますが、昔トルコ航空ある事故がありました。
アムステルタム空港への進入中に、電波高度計という飛行機から地面に向かって電波を飛ばして、その電波が跳ね返ってくるのを利用して自機の高度を測る計器がありますが(非常に正確な高度が測れます)、これが故障しました。
単なる計器の故障であればさほど怖いことではないのですが、その機体は電波高度計の高度を用いて着陸時にパワーを絞るように設計されていたので、高高度で電波高度計が故障した際に、オートパイロットがもう着陸段階だと勘違いをしてパワーを絞ってしまい、墜落しました。
この事故においてはオートパイロットのもつ危険性と、何故パイロットはそれに対処できなかったのかの両方に焦点を当てるべきなのですが、今日はオートパイロットにのみ焦点を当てて話を進めます。
この事故一つを持ってオートパイロットには任せられないと言いたいのではありません。
オートパイロットなんて所詮そんなもんなんだと僕は思っています。
この点についてもう少し掘り下げてみると、まずはそもそもオートパイロットが壊れてしまったり、コンピュータがフリーズしたり、電源がロスしてしまった時にどうするんだ?という疑問があります。
これに対して設計者としてはコンピュータなどのシステムを3つずつ積んでいて、これが同時に壊れる可能性は限りなく0に近く…という話になるのでしょうが、確かにそれぞれ独立して考えた場合に全部のシステムが故障する確立は非常に低いのでしょうが、例えば巨大な雷に打たれて電気回路が全部焼けました、なんて場合には多重のシステムを積むという冗長性は意味のないものになります。
コンピュータをたくさん積んだけど、OS自体にバグが合って…なんて場合にも同様でしょう。
揚げ足取りのようなことを言っているように見えるかもしれませんが、人の命がかかっている以上、そういった可能性に全て対応していかなければなりません。無人機ならば墜落してもお金がもったいないだけですが、旅客機はたくさんの人が乗っています。
UAV (Unmaned Aerial Vehicle)と旅客機ではそういう点で、求められる「完全性」というものがまるで別次元なのです。UAVで出来たから旅客機でも…と言うのは短絡的だと思います。
もう一点、コンピュータにはない人間の強みとして、「不足の事態にある程度対応できる」ということがあります。
上のトルコ航空の事故のように明らかにおかしいものや、「え?なんかおかしくない?」という違和感のようなものもあります。そんな場合に人間ならば「とりあえずゴーアラウンドして進入をやり直すか」なんて判断もできますが、コンピュータはそうはいきません。言ってみれば、オートパイロットとは正確にフライトをしてくれるけど、「もしかしたら自分は間違っているかもしれない」とは1mmも疑わない視野の狭い人のようなものです。
人工知能の発達によりどこまで人間に近いコンピュータが出来るのかは分かりませんが、まずはその技術ができて、そして数えきれないほどテストをして実績を作って、そして倫理的、生理的に多くの人に受け入れられて、されに法律的な整備がされて、それでやっと実現できるのがパイロットのいないフライトでしょう。僕の感覚では、今の段階からはまだまだSFの話に思えます。
と、ここまでが僕の考えですが、上の質問にあったWiredの記事についての話に移りましょう。
>「航空業界では、パイロットが操縦せずに旅客機を運航することが実現可能かどうか、激しい議論が繰り広げられている。」の議論は具体的にどのような内容であるのか。
正直言って、エアラインにいてそんな話は聞いたことがありません。
上でいう航空業界が何を指しているのかは分かりませんが、おそらくUAVなどを研究している場所での議論なのだと思います。
あとは大学ではUAVや地上から操作する飛行機の研究の話を聞いたことがありますが、いずれも僕にはよくわかりません。
>「満員の旅客を乗せた無人操縦機など想像できないという」エアバス社の見解はどういった根拠に基づくものであるのか。
うーん、これもよくわかりません。でも僕は上に書いたような理由で、エアバスと同じ意見です。
なかなか僕ももっと深く考えないとよくわからないテーマですが、現時点で僕が思うのはそんなとこでしょうか。
以上。疑問や反論なんかも大歓迎なので、また質問して下さい。