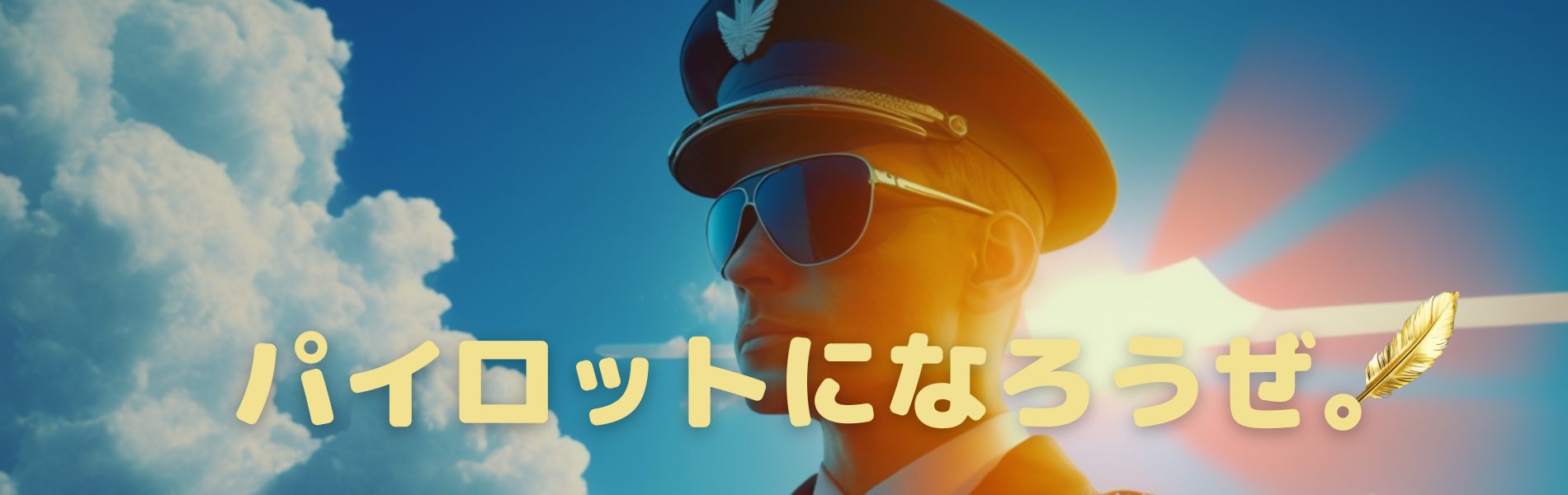色弱ではパイロットになれませんか?
はじめまして、高1の者です。
私は幼いころからパイロットを目指していました。そこで小学生の頃、航空身体検査の存在を知り、それについて親に話たら色弱であるといわれました。
信じられず、眼科医に2回検査してもらったところやはり色弱とのことでした。ですが、日常生活にはなんの支障もきたしませんし、友人などに打ち明けても普通にわかってるじゃんという感じです。
それでも、航空身体検査ではだめなのでしょうか?
あと、第1種と第2種がありますが、この2つで色覚に関する検査基準の違いがありましたら、教えていただきたいです。
もし日本の検査でだめなのであれば、海外の色覚検査基準の緩い国の操縦資格を取得してそこでだけでもいいので空を飛びたいと考えています。このことについては、どう思いますか?是非、意見などをお聞かせください。
いろいろとあって長くなってしまいましたが、ご回答いただけると幸いです。
By ヒト科のエビさん
回答
ヒト科のエビさん、ご質問ありがとうございます。
また先を越されてしまいましたが、息子をパイロットにしたい眼科医さん、早速のコメントをありがとうございます。(コメント欄に入れさせていただきました。まずコメントを確認してください。)
さて、目に関しては僕よりも専門医の意見の方に耳を傾けるべきなのですが、僕の思うところを書いていきます。
まずパイロットに色覚が必要だとされる理由は、主に2つかなと思います。
一つ目はコックピットの計器は色によって情報分けがされています。
基本的には緑が正常、オレンジが注意、赤が警報、青が作動状態などです。
これはライトの色もそうなっているし、グラスコックピットと言って、メインとなる計器がデジタル表示になっている飛行機では(ほとんどの旅客機はこれです)、何かが壊れてますよってメッセージがこの色で文字として出てきます。
だから色弱の程度にもよるとは思いますが、ライトの色が判別できないといけないし、デジタル表示が読めない、ということがあるかもしれません。
二つ目の理由は、パイロットはATCと無線通信で情報をやり取りしますが、この無線が壊れてしまった時の信号が決められています。
『ライトガン』と言いますが、管制塔からパイロットに向かって色のついた光を当てて、意思を伝えます。
これも色によって意味が違って、緑が『着陸してよし』赤は『ゴーアラウンドしろ』とか、様々に決まっていますが、これは管制塔との距離があるとか、日中帯では非常にみづらいです。
これらの理由で航空身体検査では色覚の検査があります。
それで検査基準についてですが、航空身体検査マニュアルにあるように、まずは石原色覚検査表で検査します。
これで基準内ならば合格、不合格ならばパネルD-15の検査を行い、これに通れば適合ということですね。(訂正しました)
パネルD-15でも基準外となってしまった場合には、残念ですが航空身体検査には適合しないということになります。
また一種、二種の区分けが色覚検査にはないので、どちらも同じ基準だと考えられます。
なのでまずは以上を確認してみてください。
さらにそれでもダメな場合に、海外の色覚の基準が緩い国でライセンスを取得することについてですが、いいんじゃないかと思います。
かかる費用に対して納得できるならばですが、なんだかんだで無線機の故障なんてほぼないし(小型機でも2つ装備されています)、セスナのような小型機では計器はアナログ表示なので、メッセージが読めなくて困るということはないと思います。
またそもそも、その国の法律が許すのであれば飛ぶことになんの遠慮もいらないと思います。
ただ、こういう決まり事はICAOという世界基準で決められていることが多いので、独自に基準がゆるい国というのは探すのが難しいかもしれません。
回答は以上です。
期待していた回答をしてあげられなかったかもしれず心苦しいですが、参考にしてみてください。