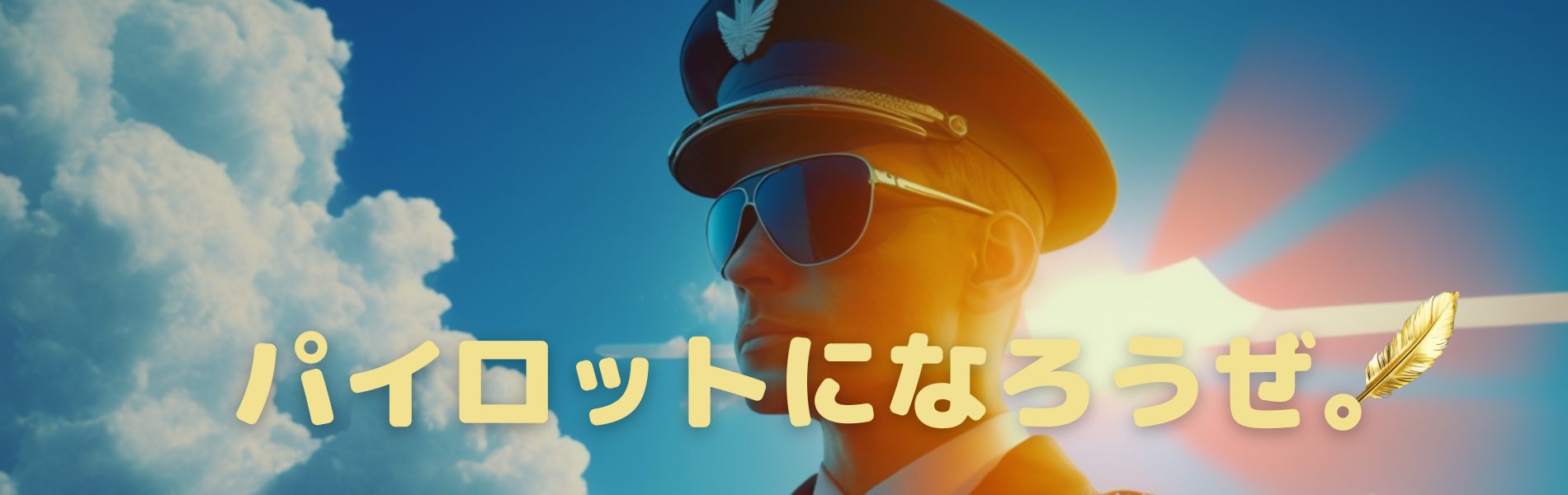続・パイロットの2030年問題
パイロットの2030年問題
だいぶ日が空いてしまったけど、ちょっとまとまった時間が取れたので続きを考えてみる。僕が勝手に考察しているだけなので、情報の真偽は自分で判断して欲しい。というか、あんまり自信がない。
まずは簡単におさらいだけど、パイロットの2030年問題とは、
LCCや機材の小型化のトレンドで運航される飛行機が増えていく中で、日本においては団塊の世代、段階ベビーの大量退職も合わさってパイロットが足りなくなってしまう、という問題のことである。
前回の記事で、意外と航空局はいい仕事をしていて、パイロットの総数としては今後足りていきそうなことがわかった。
でもよく考えると、飛行機は機長と副操縦士のワンセットでなければ運航できないんだから(ダブルキャプテンはOK)、機長と副操縦士を一緒にしてパイロットの総数を考えるだけじゃ不十分で、同時に各社が順調に機長昇格を進められないと結局のところ必要な数の飛行機を飛ばすことができない。
それで日本の各エアラインがどれくらい年間に機長昇格させているのか、IR情報とかいろんなところを調べてみたんだけど(一般に公開されている情報)、どこにも書いてなかった。
僕の調べ方が悪かったのかもしれない。誰かわかる人がいたら教えて欲しい。
だから分かりません。
それじゃあまりにひどいので、マクロな視点から考えてみようと思う。思考実験のようなものなので、真偽は相当怪しいとは思うが。
航空局の頑張りの成果で、年間に400人のパイロット候補生がエアラインに送り込まれていると言っちゃったんだけど、実は違う。
正しくは『パイロット訓練の場』に送り込まれている。
実際には全員がそのままパイロットになれるわけではなくて、自社養成や航空大では1割くらいが訓練の途中でフェイルしてしまう。
フェイル率はソースによって異なるので一概に決めてしまうのはあれなんだけど、もう少しマイルドにして5%としよう。すると400人のパイロット候補生のうち、副操縦士として操縦桿を握ることになるのは380人ということになる。
つまり入り口の時点で『やっぱ足りてないじゃん』って気もするんだけど、それは置いといて話を続ける。
パイロット訓練生から副操縦士になるのにもみんな大変な努力をしているんだけど、実は副操縦士から機長に昇格するのはもっと大変。
言い方を変えると、訓練生から副操縦士に昇格できない確率よりも、副操縦士から機長に昇格できない確率の方がずっと高い。
それにはいろんな理由があって、単純に実力や努力不足の結果ということもあるし、途中で航空身体検査が通らなくなってしまってフライト自体ができなくなってしまう人も出てくるし、ごく少数だけどパイロットの職を自分から辞める人もいるし、海外の航空会社に羽ばたいて行く人もいる。
また会社の体制の問題で、組織としての問題で機長昇格訓練がうまく進められていない会社もある。
それらを考慮すると、これもざっくり僕の感覚ということになってしまうんだけど、副操縦士に昇格した人のうち、8割程度が機長に昇格できる。という感じになる気がする。
5年で機長昇格できる会社もあるし、10年以上昇格に時間のかかる会社もあるので正確なことは言えないんだけど、僕の頭ではこれが限界。
すると年間380人の副操縦士の数の増加と同時に、機長の数の増加数は304人ということになる。これは減ったね。
本来は副操縦士も機長も400人ずつ増えなければならなかったはずだ。
機長に関しては100人足りない。
この状況が続くならば、やっぱり機長に関しては各社取り合いになってしまうんじゃないかと思える。
というか、すでに取り合いが起こっている。
これって業界の構造上の問題なんじゃないかと思うんだけど、政策として航空局はパイロット候補生の数を増やすことはできるけど、一方でエアラインに対しては副操縦士や機長の能力がない人は昇格させるなよというプレッシャーを与える存在になる。
安全のためだからしょうがないんだけど、政策としてできるのはここが限界で、フェイル率を考慮するならばそれを見越してより多くのパイロット候補者をエアラインに送り込むことしかできないんじゃ?という気がする。
このままだと、パイロットの2030年問題、やっぱり起こってしまうんじゃないかと僕は予想する。みんなはどう思うだろう?
でもこの問題は業界にとっては問題なんだけど、パイロット当人やこれからパイロットになろうとしている人には吉報でもあると思う。