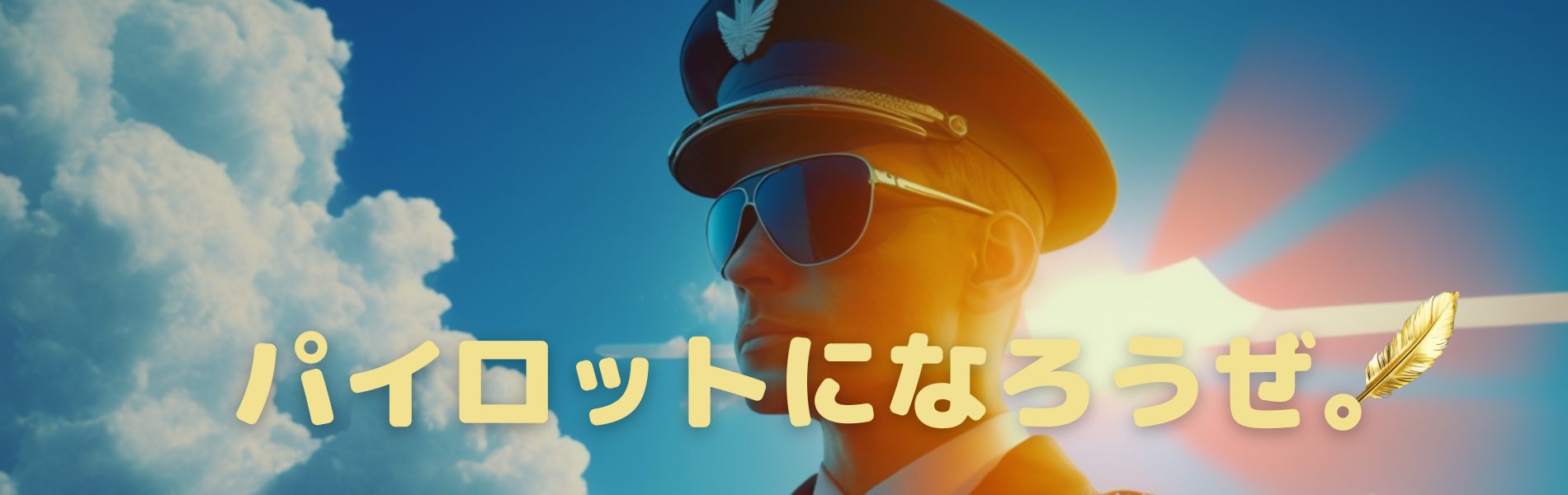コックピットのジャンプシート、航空界に必要な研究について。
はじめまして。現在アメリカで航空宇宙工学の博士課程をしている学生です。
コックピットのジャンプシートに関する質問です。
私は高校生の頃から航空業界に興味を持ち、元はパイロットを目指していましたがパイロットのライフスタイルや仕事内容について(特にこのブログを通して)知り、自分には研究や物作りが向いていると判断し学問を追求してきました。いずれは自家用操縦士のライセンスを取ろうと思っていますが、やはり大型機から見える空の景色とは比べ物になりません。なので、パイロット以外の職種で大型旅客機のコックピットで飛べる人はどんな人なのかご存知でしたら知りたいです。
もう一点、もし現在の航空業界について「こういう研究があれば安全性・環境への影響・飛行時間が良くなるんじゃないか」と思うことがありましたら知りたいです。AIやドローンなどの斬新なテクノロジーの導入についてではなく、今あるシステムを改良する・少しずつ進化させるために何が必要か、パイロットからの目線で思うことがあれば教えてください。
最後に、ブログを長年続けてくださりありがとうございます。パイロットへの憧れは高校生の時も大学院生の今も変わらず、学業や研究が大変な時にここの記事をを読むと沈んでいた心にまた火がつきます。
お時間ありがとうございます。
By 茶とらの猫さん
回答
茶とらの猫さん、ご質問ありがとうございます。
学問の追求、いいですね。僕には進めなかった道ですが、日本人にそういう人が増えればもっと強い日本になると思います。また長年このブログを読んでくれてありがとう。君のような人がいることが、僕にとっても大きなモチベーションになります。
さて、パイロット以外の職種で旅客機のジャンプシートを使える人は、自社関係者や航空局関係者、管制官のオブザーブなどかなと思います。
自社の人間なら誰でも乗れるということではなく、客室乗務員やディスパッチャーがパイロットの業務を実際に見て自分の業務に活かすために乗る場合や、技術関係の部署が新しいシステムの導入の試験とかでジャンプシートに乗ることがあります。
航空局関係者は局のパイロット、試験官によるオブザーブ意外にはこれもやはり新たな飛行方式などのシステム導入とか、無線局のテストをする職の人とか、そのような人たちが社外からもオブザーブに来られます。
昔はコックピットへの入室はゆるかったんですが、アメリカの9.11以降はめちゃくちゃ厳しくなってしまいました。パイロットの家族でももちろん入れないし、正当な理由がなければ入れません。子供に職場見学をさせてあげられないのが残念ですね。
しかし大型機のコックピットから見る景色も、小さな飛行機で低い高度から見る景色もどちらも素晴らしいものですよ。大型機でも路線が短い場合とかは低い高度を飛ぶことがありますが、よりリアルに地上の風景が見えて、僕はそちらの方が好きです。高度が上がれば上がるほど、見える範囲は増えますが世界地図みたいに現実感を失っていきます。一方でそこから見る日の出なんかは感動的でもありますが。
2点目の質問「こういう研究があれば安全性・環境への影響・飛行時間が良くなるんじゃないか」ということについてですが、やはり思い浮かぶのは『脱炭素化』でしょうか。
航空の分野に限らずですが、脱炭素化については日本は世界に遅れていて、なんなら周回遅れくらいのレベルです。日本ではあまり危機感をもったニュースとして目にしませんが、世界では『このペースで気温が上がると20年後には海水面が何センチ上がって、それに伴い日本の海面に近い場所の災害リスクがこれだけ上がる』というレポートまであります。
しかしそれくらい達成するのが難しいというのが事実で、何かブレイクスルーが…というのはハードルが高いと思いますが、小さな燃費の改善だけでも飛行機の数を考えると大きな脱炭素化に繋がります。
少しでも軽い素材を開発する。少しでも燃焼効率の高いエンジンを開発する。少しでも抵抗の少ない翼を開発する。地味なことですが環境には確かに意味があることだと思います。またパイロットとしての目線で言うと、技術だけではなく航空システム全体として整備するとよりいいんだろうなと思います。例えば全ての飛行機の速度を揃えてしまえば、より混雑空港でもスムーズに(移動距離が少なく)着陸できるし、燃料や騒音の改善にもつながります。管制官の仕事も楽になりますね。また各空港のアプローチ方式とか管制方式なんかも改善の余地があるかもしれません。
単一の航空機…として見るのではなく、もう少し広い視点でものを見ると発見できることがあるかもしれません。実現のハードルは上がるでしょうが。
またそうは言っても小さな改善では増える航空需要の中でジリ貧になっていくだろうと思われるので、どこかで大きなブレイクスルーが必要になるんじゃないかなと思います。それがどういうものなのかは、僕よりも君の方が詳しいと思います。またそれができるのは、やはり研究者です。
僕がいうのもアレですが、だから日本の優秀な学生には是非とも研究への道を進んで欲しいし、研究者の待遇をあげるなど社会的な整備も必要だと思います。
夢と希望を持って頑張って欲しいです。またなんでも聞いてください。逆に未来の技術について、教えて欲しいと思います。